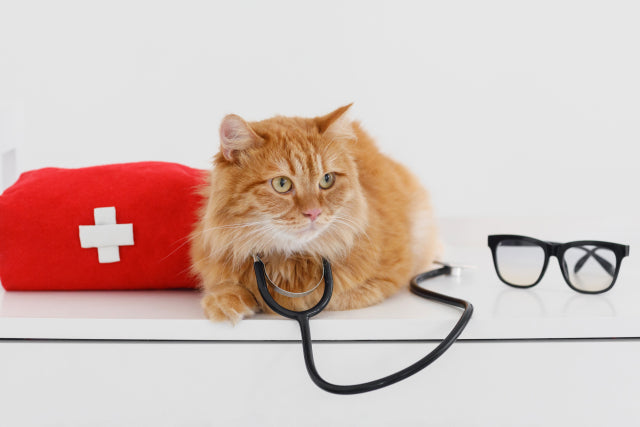
猫の健康診断の費用はいくら?検査内容・必要性・病院嫌いな子の対策まで獣医師が解説
Table of Contents
- そもそも猫に健康診断は必要?飼い主が知っておくべき2つの理由
- 理由1:猫は不調を隠すのが得意な動物だから
- 理由2:病気の早期発見・適切な健康管理に繋がるから
- 猫の健康診断はいつから?年齢別の推奨頻度と検査内容
- 【年齢別】健康診断の推奨頻度
- 子猫(〜1歳):年1回以上
- 成猫(1〜6歳):年1回
- シニア猫(7歳〜):半年に1回
- 基本的な検査内容と目的
- 問診・視診・触診・聴診
- 血液検査
- 尿検査・便検査
- レントゲン検査・超音波(エコー)検査
- 【本題】猫の健康診断にかかる費用の目安は?
- 基本的な健康診断の費用相場:5,000円〜20,000円
- 【比較表】動物病院の健康診断プランと料金例
- 健康診断の費用を抑える3つの方法
- ペット保険の活用を検討する
- 動物病院のキャンペーンを利用する
- 日頃の健康管理で病気を予防する
- ペット保険は健康診断の費用に使える?
- 病院嫌いな猫を健康診断へ!飼い主ができる4つの準備とコツ
- 1. キャリーケースを「安心できる場所」にする
- 2. 洗濯ネットを上手に活用する
- 3. 事前に病院へ「病院が苦手」と伝えておく
- 4. 往診や猫専門病院も選択肢に入れる
- 健康診断の後も安心!結果の見方と自宅でのケア
- 健康診断の結果、どう見る?獣医師からの説明をしっかり聞こう
- おうちでできる!日々の健康チェックリスト
- 猫の健康診断に関するよくあるご質問
- まとめ:愛猫の健康のために、定期的な健康診断を
- 猫の健康診断の費用は、基本的な検査で5,000円~20,000円が目安ですが、病院や検査内容によって変動します。
- 猫は不調を隠す習性があるため、病気の早期発見とその後の適切なケアのために定期的な健康診断が非常に重要です。
- 推奨頻度は年齢によって異なり、成猫は年1回、7歳以上のシニア猫は半年に1回が推奨されます。
- 病院嫌いの猫には、キャリーケースに慣らす、洗濯ネットを活用する、事前に病院に相談するなどの対策が有効です。
そもそも猫に健康診断は必要?飼い主が知っておくべき2つの理由

「うちの子は元気そうだし、健康診断は本当に必要なのかな?」初めて猫を飼う飼い主さんなら、そう思うかもしれません。しかし、猫にとって定期的な健康診断は、私たちが考える以上に大切な意味を持っています。その理由は、猫ならではの習性に関係しています。
ここでは、飼い主さんが知っておくべき2つの大きな理由について、優しく解説します。
理由1:猫は不調を隠すのが得意な動物だから
猫の祖先は、自然界で単独で生きてきました。そのため、外敵に弱みを見せないよう、痛みや不調をギリギリまで隠す習性が今も残っています。飼い主さんの目には元気そうに見えても、実は体内で静かに病気が進行していることも少なくありません。飼い主さんが「なんだか様子がおかしい」と気づいたときには、病気がかなり進行してしまっているケースもあるのです。
理由2:病気の早期発見・適切な健康管理に繋がるから
定期的な健康診断は、そんな「隠れた不調」を見つけ出すための最も有効な手段です。症状が出る前に病気のサインを発見できれば、早期に愛猫の体調変化に応じたケアを開始できます。これは、愛猫の身体的な負担を軽くするだけでなく、結果的に長期的な治療にかかる費用や、飼い主さんの心の負担を軽減することにも繋がります。大切な家族である愛猫と一日でも長く健やかに過ごすための、重要な投資なのです。
猫の健康診断はいつから?年齢別の推奨頻度と検査内容
猫の健康診断は、ライフステージによって推奨される頻度や検査内容が異なります。人間の年齢に換算すると、猫は1年で約4歳も年をとるといわれています。そのため、猫にとっての「1年に1回」は、私たち人間にとっての「4年に1回」に相当します。
ここでは、愛猫の年齢に合わせた健康診断の受け方について見ていきましょう。
【年齢別】健康診断の推奨頻度
猫の成長スピードに合わせて、健康診断の頻度を調整することが理想的です。以下に年齢別の一般的な目安をご紹介します。
子猫(〜1歳):年1回以上
子猫の時期は、ワクチン接種や寄生虫の駆除などで動物病院へ行く機会が多いでしょう。その際に、基本的な健康チェックも一緒に行うのが一般的です。先天的な病気がないかなどを確認し、健康な体づくりの基礎を築く大切な時期です。
成猫(1〜6歳):年1回
心身ともに充実する成猫期は、年に1回の健康診断が推奨されます。この時期に定期的に検査を受けることで、その子の「健康なときのデータ」を蓄積できます。将来、何かしらの異常が見つかった際に、この平常時のデータが非常に重要な比較対象となります。
シニア猫(7歳〜):半年に1回
7歳を過ぎるとシニア期に入り、腎臓病や心臓病、甲状腺機能亢進症といった加齢に伴う病気のリスクが高まります。そのため、半年に1回のペースで、よりきめ細やかな健康チェックを行うことが推奨されます。病気の兆候をいち早く捉えることが目的です。
基本的な検査内容と目的
健康診断では、具体的にどのようなことを調べるのでしょうか。ここでは、多くの動物病院で行われている基本的な検査項目とその目的を簡単にご紹介します。
問診・視診・触診・聴診
飼い主さんから普段の様子(食欲、飲水量、排泄など)を聞き取り(問診)、獣医師が目で見て(視診)、体に触れて(触診)、聴診器で心臓や肺の音を聞き(聴診)、全身の状態をチェックします。最も基本的ながら、多くの情報が得られる重要な診察です。
血液検査
少量の血液を採って、目には見えない体の中の状態を調べます。赤血球や白血球の数から貧血や炎症の有無を、様々な数値から肝臓や腎臓といった内臓の働きに異常がないかなどを確認することができます。病気の早期発見に欠かせない検査です。
尿検査・便検査
尿からは腎臓の機能や膀胱炎、尿石症などの病気のサインを、便からは消化器系の状態や寄生虫の有無などを調べます。自宅で採尿・採便して持参するケースが多いため、事前に病院に方法を確認しておくとスムーズです。
レントゲン検査・超音波(エコー)検査
これらはオプション検査となることが多いですが、体の内部を画像で確認するために行われます。レントゲン検査は骨や胸部、腹部全体の臓器の形や大きさを、超音波検査は臓器の内部構造をより詳しく見るのに役立ちます。
【本題】猫の健康診断にかかる費用の目安は?

愛猫の健康のために重要だとわかっていても、やはり気になるのが費用ですよね。猫の健康診断にかかる費用は、動物病院や検査項目の内容によって大きく異なります。ここでは、飼い主さんが事前に知っておきたい費用相場や、料金プランの例、そして費用を少しでも抑えるための方法について解説していきます。
基本的な健康診断の費用相場:5,000円〜20,000円
基本的な健康診断(問診、身体検査、血液検査、尿・便検査など)の場合、費用はおおむね5,000円~20,000円程度が目安とされています。比較的若い猫向けのシンプルなプランであれば10,000円以下で受けられることもありますし、シニア猫向けにレントゲン検査や超音波検査などの詳細な項目が含まれたプランでは、20,000円を超えることもあります。費用が気になる場合は、事前に動物病院のウェブサイトを確認したり、電話で問い合わせておくと安心です。
【比較表】動物病院の健康診断プランと料金例
多くの動物病院では、年齢や目的に合わせた「健康診断パッケージプラン」を用意しています。ここでは、一般的なプランの例を比較表にまとめました。あくまで一例として、ご自身の愛猫に合ったプランを考える際の参考にしてください。
|
プラン名 |
対象年齢(目安) |
主な検査項目 |
費用相場 |
|---|---|---|---|
|
ベーシックプラン |
1歳~6歳 |
問診、身体検査、血液検査(基本的な項目)、尿検査 |
8,000円~15,000円 |
|
シニアプラン |
7歳以上 |
ベーシックプランの内容 + レントゲン検査、超音波検査、甲状腺ホルモン検査など |
15,000円~30,000円 |
健康診断の費用を抑える3つの方法
定期的にかかる費用だからこそ、少しでも負担を抑えたいと思うのは自然なことです。ここでは、健康診断の費用を賢く抑えるための3つの方法をご紹介します。
ペット保険の活用を検討する
ペット保険は基本的に「病気やケガの治療」を対象とするため、予防医療である健康診断は補償対象外となるのが一般的です。しかし、保険会社によっては特定のプランや特約で健康診断の費用を補助してくれる場合もあるため、加入を検討する際は確認してみましょう。
動物病院のキャンペーンを利用する
動物病院によっては、春や秋の過ごしやすい時期に「健康診断キャンペーン」を実施していることがあります。通常よりもお得な価格で検査を受けられることが多いので、かかりつけの病院のウェブサイトやお知らせをチェックしてみるのがおすすめです。
日頃の健康管理で病気を予防する
大切な方法のひとつは、日頃から愛猫の健康管理をしっかり行い、病気になりにくい体づくりをサポートすることです。バランスの取れた食事や適度な運動、ストレスのない環境を整えることが、結果的に将来の医療費を抑えることに繋がります。
ペット保険は健康診断の費用に使える?
多くの飼い主さんが疑問に思う点ですが、原則として、ペット保険は「予防」目的の健康診断の費用には適用されません。ペット保険は、あくまで病気やケガをしてしまった際の「治療費」を補償するためのものです。
ただし、健康診断の結果、何らかの異常が見つかり、その診断のために追加の精密検査や治療が必要になった場合、その部分の費用は保険の補償対象となることが一般的です。契約内容によって詳細は異なるため、ご自身の保険の規約を一度確認しておくことが大切です。
病院嫌いな猫を健康診断へ!飼い主ができる4つの準備とコツ

「健康診断の重要性はわかったけれど、うちの子は病院が大嫌いで…」そんな悩みを抱える飼い主さんは少なくありません。猫にとって、慣れない場所へ連れて行かれることは大きなストレスです。でも、少しの工夫と準備で、猫と飼い主さん双方の負担を大きく減らすことができます。
ここでは、病院嫌いの猫ちゃんをスムーズに健康診断へ連れて行くための、今日からできる4つのコツをご紹介します。
1. キャリーケースを「安心できる場所」にする
キャリーケースを「病院に行くときだけ出てくる怖い箱」にしないことが大切です。普段から部屋の中に置いておき、自由に出入りできるようにしましょう。中に猫ちゃんのお気に入りの毛布やおやつを入れて、「ここは安全で快適な場所」だと教えてあげると、いざという時の抵抗感が和らぎます。
2. 洗濯ネットを上手に活用する
意外に思われるかもしれませんが、洗濯ネットは病院嫌いの猫ちゃんにとって心強い味方です。大きめの洗濯ネットにすっぽり入れてあげることで、猫は適度に視界が遮られ、体が包まれることで安心感を得やすいとされています。また、診察の際に猫が暴れてしまうのを防ぎ、獣医師やスタッフの安全を守る役割も果たします。
3. 事前に病院へ「病院が苦手」と伝えておく
予約の際に、「うちの子は病院がとても苦手で…」と一言伝えておくだけで、病院側の対応も変わってきます。他の動物が少ない時間帯を提案してくれたり、診察室で少し落ち着く時間をくれたりと、様々な配慮をしてくれることがあります。事前に情報を共有しておくことで、お互いに心の準備ができます。
4. 往診や猫専門病院も選択肢に入れる
どうしても通院が難しいほどのストレスを感じる猫ちゃんの場合は、無理をしないことも大切です。最近では、自宅まで来てくれる「往診専門」の獣医師や、待合室に犬がいない「猫専門病院」も増えています。費用は少し高くなるかもしれませんが、愛猫のストレスを最小限に抑えるための有効な選択肢として検討してみましょう。
健康診断の後も安心!結果の見方と自宅でのケア
健康診断は、受けて終わりではありません。その結果を正しく理解し、日々の暮らしに活かしていくことが大切です。検査結果に一喜一憂するのではなく、愛猫の健康状態を把握し、今後のケアに繋げるための貴重な情報と捉えましょう。
ここでは、診断後の結果の聞き方や、おうちでできるケアについて解説します。
健康診断の結果、どう見る?獣医師からの説明をしっかり聞こう
検査結果の数値が並んだ紙を見ても、専門家でなければ理解するのは難しいものです。大切なのは、獣医師からの説明をしっかりと聞くこと。「この数値は何を意味するのですか?」「正常値と比べてどうですか?」など、わからないことは遠慮せずに質問しましょう。もし異常が見つかった場合でも、今後の治療方針や生活で気をつけるべきことについて、丁寧に説明してくれます。結果の用紙は必ず保管し、次回の健康診断の際に持参すると比較に役立ちます。
おうちでできる!日々の健康チェックリスト
動物病院での定期的なチェックと合わせて、飼い主さんが毎日できる「おうちでの健康チェック」も非常に重要です。日々の小さな変化に気づくことが、病気の早期発見に繋がります。以下の項目を参考に、愛猫の様子を観察する習慣をつけましょう。
- 食欲・飲水量:いつもと比べて多すぎたり少なすぎたりしないか
- おしっこ・うんち:色、量、回数、硬さはいつも通りか
- 体重:急に増えたり減ったりしていないか
- 被毛・皮膚:毛づやは良いか、フケや脱毛はないか
- 動き方:歩き方やジャンプに変化はないか
猫の健康診断に関するよくあるご質問
ここでは、猫の健康診断に関して飼い主さんからよく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 検査の前に絶食は必要ですか?
A1. 血液検査を行う場合、食事が血糖値などの数値に影響を与えることがあるため、一般的に検査前の8〜12時間程度の絶食・絶水が推奨されることが多いです。ただし、猫の年齢や健康状態によっても異なるため、必ず事前に動物病院に確認してください。
Q2. 健康診断で異常が見つからなかった場合でも、受ける意味はありますか?
A2. はい、非常に大きな意味があります。異常がないということは、その時点での「愛猫の健康な状態」をデータとして記録できたということです。この平常時のデータがあることで、将来何かの異常が出たときに、どれくらい変化したのかを正確に比較でき、診断の大きな助けになります。
Q3. 尿や便はどうやって持っていけばいいですか?
A3. 尿は、システムトイレの場合は下のシートを裏返したり、ペットシーツを抜いておくと溜まったものをスポイトで採取できます。普通のトイレの場合は、砂を少量にして採取する方法もあります。便は、なるべく新鮮なものをラップやビニール袋に包んで持参しましょう。採尿・採便が難しい場合は、病院で対応してくれることもあるので、無理せず相談してください。
まとめ:愛猫の健康のために、定期的な健康診断を
愛猫の健康診断は、言葉を話せない彼らのための、飼い主さんができる最高のプレゼントの一つです。費用や病院へ連れて行くことへの不安もあるかと思いますが、この記事でご紹介した情報を参考に、ぜひ一歩を踏み出してみてください。定期的な健康診断が、愛猫との健やかで幸せな毎日を、一日でも長く支えてくれるはずです。
愛猫の健康な毎日をサポートするサプリNUTREATS

NUTREATSは、100%天然のモエギイガイオイルを豊富に配合した猫用オメガ3サプリメントです。 自然由来の成分だから長期使用も安心、薬との併用も可能です。 オメガ3脂肪酸の含有量は1粒あたり約30mg!
熱に弱く酸化しやすいオメガ3脂肪酸を壊さずに抽出する独自の製造方法により、30種類以上の必須脂肪酸を高度に精製し、食品グレードの工場で、HACCPおよびGMP基準(国際的な製造品質管理基準)の厳しい規制に従って製造されています。もちろん、防腐剤、増量剤、添加物、香料、着色料は一切使用していません。
モエギイガイには、オメガ3脂肪酸の他、関節の潤滑油的な役割を担うコラーゲンやヒアルロン酸、各種アミノ酸などの成分も豊富に含まれています。
毎日手軽に取り入れられるサプリメントで、愛猫の健やかな毎日をサポートしましょう。





